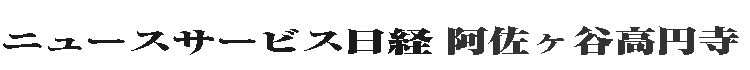君の罪の子 我も罪の子
第3回 愛・理性・勇気〜与謝野晶子伝説 その3
語り手:大江戸蔵三
都内の某新聞社に勤める整理部記者。三度のメシより歴史が好きで、休日はいつも全国各地を史跡めぐり。そのためか貯金もなく、50歳を過ぎても独身。社内では「偏屈な変わり者」として冷遇されている。無類の酒好き。
聞き手:杉並なぎさ
都内の某新聞社に勤める文化部の新米記者。あまり歴史好きではないのだが、郷土史を担当するハメに。内心ではエリートと呼ばれる経済部や政治部への異動を虎視眈々と狙っている。韓流ドラマが大好き。
17歳で一家の大黒柱に
前回、父の宗七が晶子が女の子というだけで拒否反応を示したという話をしたけど、反面、宗七は凄く教育熱心で、3歳の晶子を無理矢理尋常小学校に入れたんだ。3歳って、まだ保育園とか幼稚園の歳でしょ。ちょっと早すぎない?
実際早すぎて、これは失敗。結局普通に小学校に通うことになって、その傍ら漢学塾で論語や漢詩を習ったりしていた。で、晶子が自我に目覚め始めるのは明治21年(1888)、堺区立女学校に入学した頃なんだ。学校のカリキュラムは裁縫なんかが主体の「良妻賢母養成所」みたいなものだったけど、当時すでに沈静化へと向かっていた自由民権運動の余波が、晶子たち女学生にも及び始めていた。
自由民権運動って、歴史の授業で習った記憶があるわ。よく覚えてないけど。
キミの脳みそは常にメモリ不足だな。そのくらい自分で調べなさいよ。晶子の著作『私の生い立ち』には新任の若い教師が12歳の晶子にこんなことを話したと書いてある。「女が裁縫さえ上手にすればいいと思うのは昔風な考えで、世界にはいろいろな国があり知恵の進んだ人が多い。日本もそれに負けていてはならない」
新しい時代の息吹を感じるわねぇ。
その頃には姉が嫁いでいたので、晶子は家業を手伝うかたわら、父の蔵書をかたっぱしから読み始める。後に現代語訳を出版する『源氏物語』に親しむのもこの頃からだ。
やっぱり晶子さんは文学少女だったのね。
女学校の本科を卒業して、補習科に進む頃には、東京の帝大に通っていた兄の秀太郎から送られてくる新刊本や文芸雑誌に夢中だったようだね。晶子の場合、父も兄も文学や芸術に理解があったから蔵書も多かった。そういう意味では、商家の娘としては恵まれた環境だったのかもしれない。
晶子さんはどんなジャンルの文学が好きだったのかな?
やはり『源氏物語』を頂点とする王朝文学だね。夢見がちな少女時代は特に、きらびやかな貴族文化に憧れていたらしい。もともと大人びた感性を持った少女だったからね。『私の生い立ち』には“三羽のひよこ”という面白いエピソードが書かれている。
“三羽のひよこ”? 何それ?
晶子が小学2年生の頃、教師が授業で質問した。「ここに三羽のひよこがあるとしまして、二羽のひよこはいま人から餌をもらって食べています。一羽のひよこはそれを見てます。そうするとその一羽のひよこはどんなことを思っていると思いますか」
なんで自分だけもらえないの?ってことでしょ、普通。
だからキミは凡人なんだよ。晶子は答えられなかった。そんなに単純じゃないし、そうたやすくわかるはずがない、私は一羽のひよこのほんとうの気持ちが知りたいと、その後何年も思い続けたそうだ。
そんな事言われたら先生だって困るでしょ。小学校2年生の発想じゃないわね。
商家の大家族の中で揉まれて育ったからね。人間の内面の複雑さを子供の頃から感じていたんだろうね。女学校を卒業した晶子は、脳溢血で母が倒れた頃から家業を一手に引き受けるようになる。
あらら、それじゃあ、本を読む時間もなくなっちゃうでしょ。
ところが晶子は以前にも増して読書家になった。外出もままならなかったから、仕事の傍ら本を読んでは夢想にふけった。そんな中で、17歳の頃には純潔な処女を理想とするようになる。友達にも結婚なんかしちゃいけないと勧めていたらしいからね。
そういえば、私もそんな時期があったな〜。
キミの少女時代なんかどうでもいいよ。兄と妹が学生で不在、父親は株で失敗して大損、母は病気という状態だったから、当時の晶子は必然的に一家の大黒柱になるしかなかった。後に夫と11人の子供を抱えて奮闘する晶子の原型がここにある。ただ、それでも文学への夢は捨てなかった。当時、文壇では樋口一葉がデビューして『たけくらべ』なんかが絶賛されていた。一葉は早世してしまったけど、女流作家という道を開いていたんだ。
偉大な先輩が道を開いてくれたから、晶子さんにもチャンスはあったわけね。
筆舌に尽くしがたい苦労の中で、晶子はその心中を兄にも妹にも語らなかった。芯から強い人なんだな。でも、そんな晶子の人生が徐々に変わり始める。それは文芸誌に送った一首の短歌がきっかけだった。
←近代女流文学の先駆者・樋口一葉